以下の項目に該当する方は
要注意です!
- 便潜血検査で陽性と診断された
- 排便後拭いた紙に血がつく事ある
- 排便後便器が真っ赤になっていた事がある
- 便が黒くなった
- 血液検査で貧血があると言われた(貧血症状を感じている)
- 健康診断で便潜血検査陽性と指摘された
- 便潜血検査で陽性と診断されたがまだ大腸の精密検査を受けていない方
- 血便が出た事がある
- 下痢や便秘など、排便のリズムや形状が変わってきた
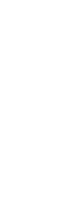
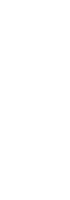
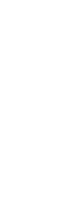
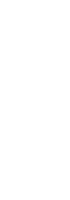
Medical
以下の項目に該当する方は
要注意です!
出血といえば真っ赤な色をイメージしがちですが「鮮紅色(血を多く含む鮮やかな真っ赤な色)」以外にも、「粘血便(粘液の混ざった赤色)」「暗赤色(薄暗い赤色)」、「黒褐色(海苔の佃煮あるいはイカ墨様)」など色調は様々です。見た目で確認できるものと、見た目では確認できず便検査をしてわかる血便もあります。
「下血」とは胃や十二指腸などの上部消化管からの出血を指す場合があり、薄暗い赤色の便が肛門から排出されます。「血便」とは真っ赤な血液が混ざった便・あるい真っ赤な血液のみが肛門から排出される事を示し、主に大腸や肛門からの出血を指します。「便潜血」とは見た目で確認できない微量の腸管からの出血の事を言い、大腸がん検診などで広く使われています。この検査では少量の出血(3〜5ml)でも異常を検出する事が出来ます。近年、増加傾向にある大腸癌は初期の段階では便の色も形も変化はなく、無症状の事が多いので便潜血検査は異常の早期発見の一助となります。
便の色、便の性状(血だけか粘液が混じるかなど)、症状(腹痛 下痢 発熱 肛門痛)、出血量、症状の経過、既往症(持病)などを考慮し、原因を特定していきます。
色の赤みが濃く鮮やかである場合は肛門もしくは肛門近くの大腸からの出血が考えられ、排便が赤暗く黒っぽい場合は胃や十二指腸からの出血が考えられます。
血便は便の色によってある程度は出血が発症している場所や原因の特定をすることができます。
などの疾患が下血・血便を引き起こす疾患として挙げられます。これらの病気はそれぞれ治療方法が異なるため、しっかりと診断をつけて治療を行う事が必要となります。
血便を放置していると、まず上記で挙げたよう疾患が悪化し、症状が進行していきます。また、出血が長期間続く事で貧血や低血圧を引き起こす事もあります。
全身を流れる血液量が低下し、酸素を全身へ運ぶヘモグロビンの量が減少してしまう事で、酸素が全身に行き届かなくなる事で貧血を発症します。貧血の症状は立ちくらみ、頭痛、動悸、爪の異常などがあります。貧血の状態が続く事で心臓にも負担がかかってしまい、心不全などの重大な疾患を引き起こす事もあります。
全身を流れる血液量が減少する事で、血圧が低下してしまいます。低血圧発症時の症状は立ちくらみ、めまい、動悸、疲労感、頭痛やひどい時には失神を起こします。
直腸診では肛門や直腸の状態を確認し、腫瘍や痔核などの有無を確認していきます。付着液を観察し、出血の有無、色や出血量などを確認します。
黒色便(タール便)がみられる場合、食道・胃・十二指腸などの上部消化管からの出血が疑われます。貧血の有無を確認し、胃カメラ検査を行い、上部消化管の粘膜上で炎症や潰瘍などが生じていないかを確認します。
胃カメラ検査大腸カメラ検査を実施し、大腸から出血していないかを調べます。大腸がんや大腸ポリープをはじめ、潰瘍性大腸炎・クローン病などの幅広い大腸の病気の早期発見に繋がります。
また病変が疑われる部位を見つけた際は組織採取・ポリープ切除・培養検査をすることもできますので、確定診断が可能となります。
大腸カメラ検査血便の予防で重要なことは、自覚症状がなくても定期的に検査・健診を受けていただくことです。定期的に内視鏡検査(特に大腸カメラ検査)を受けることで、自覚症状がない段階の早期がんやがんになる前の病変を発見することができます。どんな病気でもそうですが早期発見・早期治療介入が大切です。大腸カメラ検査を定期的に受けていただき、病気の早期発見ができれば、普段の生活やお仕事に支障なく完治することが可能となります。
また、黒色便(タール便)がみられる際は胃カメラ検査で上部消化管の粘膜の状態を確認していきます。また胃カメラ検査では粘膜の確認だけではなく、併せてピロリ菌感染の有無も調べることができます。ピロリ菌に感染している場合は除菌治療を受けていただく必要があります。除菌治療が成功すると炎症や潰瘍の再発を効果的に抑制することができ、また胃がんの発症リスクを抑えることにも繋がります。
血便でお困りの方、血便が一度でも出たことがある方はご自身の健康状態をしっかりと把握をしていただくためにも定期的に内視鏡検査を受診していただきたく思います。血便の診察や内視鏡検査のことならお気軽にご相談ください。
血便が出たとしても「自分はまだ若いから大丈夫!」「ただの痔だと思うから大丈夫!」「1回しか血便が出てないから大丈夫!」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、本来であれば消化管から出血が生じることはありませんので、血便が出た際はお腹の中で異常が生じているサインでもあります。
最近では食生活の欧米化が進んでいたり、生活習慣の変化などの要因もあり、若い方でも大腸がんに罹患してしまう方も増えております。大腸がんは発症していても特に自覚症状を感じにくい特徴がありますが、そんな大腸がんですが『血便』は大腸がんの初期症状としてよくみられる症状です。
血便が出た際は出血の程度に関わらずお早めに当院までご相談してください。当院では消化器内視鏡専門医の資格を持っている医師が血便の診察や治療、内視鏡検査を行っております。些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
